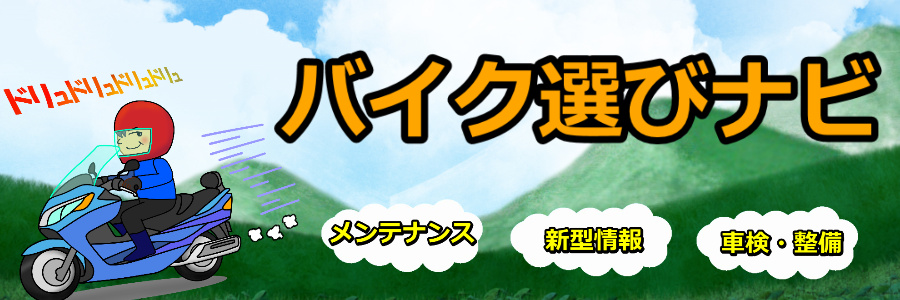車検義務があるバイクに乗っている人は、保安基準に適合したマフラーを取り付けていないといけません。
しかし、バイクをカスタムしたい人にとっては、マフラー交換は必須の作業と言えます。
よりカッコイイバイクに乗りたい人に、マフラーの保安基準についてをお伝えしていきます。
バイクのマフラーは交換してはいけない?
整備完了した😚
【本日の作業内容】
・プラグ交換
・エンジンオイル交換
・ブレーキフルード交換
・スロットルワイヤー調整
・マフラー交換
・カウル交換
・車高調整車高7mm上げたら、身長177cmのワイでも両足ベタでつかなくなったwww
やっぱバイクはケツ上がりがエエよな🤤 pic.twitter.com/GGxcJMct2b
— はちりや (@hachiriya8) September 19, 2021
バイクのマフラーは交換してはいけない法律はありませんが、保安基準に適合しないマフラーの取り付けは禁止されています。
マフラーくらいは自分でも交換ができるレベルですが、一番注意したいのが購入時なのです。
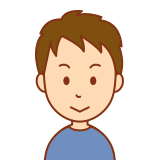
では、簡単にマフラーの構造についても、簡単に説明していきましょう。
マフラーは高音や高圧の排ガスをそのまま排出しているわけではなく、内部にサイレンサーが組み込まれていて、サイレンサーの構造によって音が外部に漏れないようにしているのです。
さらに、マフラーには排気ガスが出る勢いを利用することによって、吸気効率を高めたり充填効率を高めるという効果もあります。
そんなマフラーには、大きく分けると以下の通りです。
・フルエキゾーストマフラー
スリップオンマフラーはサイレンサー部分だけの交換になるので、カスタムもかなり簡単と言えます。
性能的に見ればフルエキゾーストマフラーよりも劣っているので、見た目だけを重視したいという人には最適かもしれませんね。
フルエキゾーストマフラーは、エンジンの根元からサイレンサー部分まで、マフラーをすべて交換することになります。
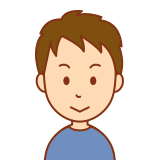
スリップオンマフラーに比べて、マフラー交換の作業は大変です。
交換自体を楽しいと感じている人にとっては、フルエキゾーストマフラーのほうが、やりがいがあるのではないでしょうか
フルエキゾーストマフラーの場合はマフラー全体を交換することになるので、性能アップが期待できます。
ただ、フルエキゾーストマフラーを交換した場合は、エンジンのほうも調整をしていく必要があるので、作業が増えます。
つまり、フルエキゾーストマフラーの交換の場合は、チューニングについての知識も少しはあったほうが良いでしょう。
マフラー全体を交換することで、バイクの雰囲気は大きく変化します。
【バイクのマフラー】保安基準が新しくなった!
#ハセガワ 1/12 TZR。自作マフラーを塗ってみました、が、チャンバー部の焼き色が難しい。数日かけてあれこれ試しましたが、今の自分にはこれが精一杯です。次に2ストバイクを作るまでに他の方法を考えておくことにします。 pic.twitter.com/oqOxeXKkcs
— るうら1067 (@qkSb0hzmoYht5zG) September 17, 2021
平成28年4月20日から、保安基準が新しくなっています。
新車時の騒音測定に加えてリプレイスマフラーも、認定時の騒音以上になっていないかというのも、車検時に検査される項目となっています。
余り知られていないかもしれませんが、マフラーは消耗品です。
そんな消耗品だからこそ、社外品に交換している人もいるでしょう。
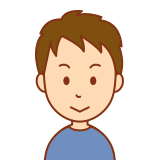
社外品マフラーだからと言って、車検に通らないというわけではありません。
イメージとしては社外品は、車検不適合と思われていますし、音量も高いと思われているのです。
サビによりマフラーに穴が開いていると、音量が大きくなり純正マフラーでも車検に通らなくなるのです。
しかし、触媒が入っているマフラーは、注意が必要です。
触媒が入っているマフラーは、マフラーを交換するだけで、保安基準に適合しなくなる可能性が高くなります。
車検時のマフラーチェックというのは、音量と排気ガスの測定が重要視されているのです。
排気ガスのチェックについては、新しい車種のみ実施することなので、古いバイクの場合は音量検査だけ通過すれば良いということになります。
マフラーの音の基準って何?
マフラー変えてもらった!
せっかくだから夜少し走りたかったのに、雨降ってきたから断念…マフラー変えただけでバイクが変わったように感じる。笑 pic.twitter.com/JZqMuKxtOV— りゅう (@ninja1000ryu) September 17, 2021
車検時のマフラー音基準は、保安基準が改正される前は絶対規制値で測定されていました。
なので新しい車種が販売される場合は、近接騒音と加速騒音基準適合の測定が行われます。
そして、認定された騒音がそのバイクの騒音として、定められるということなのです。
新型バイクが販売されるときは、事前に国土交通省の型式認定を受けなくてはいけません。
しかし、現に出回っているバイクに関しては、新しい保安基準は適合されていないので、事情は異なるということです。
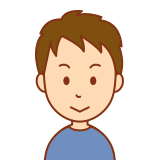
マフラーに関しても認定を受けている場合は、使い続けることができます。
さらに、認定を受けているマフラーは、認定証明書というものが必要になるのです。
騒音測定方法について
マフラー音量測定。
2年前は95dBでギリギリ?だったけど、ウール交換したエトスの音量は88.7dBとグッと静かになりました(^ ^) pic.twitter.com/vlzhkZLg3C— ロスマ35 (@rothma35) May 20, 2020
近接騒音測定はマフラー端から45度後方の同じ高さで、距離50メートルに音量測定マイクを設置して測定をします。
定常走行騒音測定の場合は、最高出力60%で走行をした速度で、7.5メートル離れた場所から測定。
以上の測定方法については、メーカーがサンプル車両を使用して計測するときにも使われています。
平成28年10月以降登録バイクの新車に、新車時に加えて車検時でも加速騒音基準適合ASEPの測定が、行われています。
取り付けが義務付けられた表示って何?
バイクでキャンプ行きたくなったので👀
車検の準備のためにマフラー(排気ガス出るところ)を純正に戻す作業をします
これ保安基準に適合してる静かなマフラーなんだけど、にやパイセン知ってます。車検場の音量計とメーカーの音量計は違うのです。たぶん車検通らないから交換。今日明日の夜仕上げる pic.twitter.com/8p4ogxPJ4v
— にや🔺 (@NiyAcccc) April 12, 2021
新車バイクを買ったり平成28年4月20以降にマフラーを交換した場合は、純正マフラーであれば「自」と書かれたマークが表示されています。
この「自」というマークは、純正品であるという意味であり、車両形式認証を受けているマフラーであるという証拠でもあります。
リプレイスマフラーの場合は、認証機関の略称や識別番号が記されたマークが、マフラーに打刻されているのです。
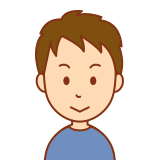
輸入バイクの場合は「協定規則適合品表示」のEマークや、「欧州連合指令適合品表示」のeマークが表示されます。
保安基準を守ったうえでのマフラー交換は合法!
マフラー交換欲求もあるけど、静かな方が楽なんだよなー。バイク乗る時でさえ疲れてるんかな。あーおもろくねえな pic.twitter.com/V1u5ky39yW
— アカマル (@akamaru_redbike) September 14, 2021
しかし、社外品マフラーでも合法のマフラーは、存在しているのです。
新たに改正された保安基準に沿った社外品マフラーなら、交換をしたとしても車検に通らないという事はありません。
中古バイクでも初めての車検では、新しい保安基準の対象になるので注意が必要です。
マフラーはカスタムをするうえで交換したくなる必須パーツですが、保安基準を守ったうえで行いましょう。
マフラー交換をするメリットとデメリット
みんなバイク乗ってるけどマフラー変える🙋♂️ pic.twitter.com/JxlKY6yHkZ
— Naom (@N99112939) September 19, 2021
バイクのマフラーを交換する場合は、色々なメリットがありますがデメリットもあります。
自分だけのことを考えるのではなく、周囲の迷惑も考えてから、どういうマフラーを選ぶのかを考えたほうが、無用なトラブルを回避できるでしょう。
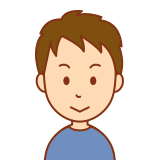
次は、マフラーを交換したときのメリットと、デメリットについてお伝えしていきます。
マフラー交換をするメリット
・自分好みの見た目にできる
・高回転がよりストレスなく回る
・軽量化が期待できる
車でもバイクでもマフラー交換をする一番の理由は、「自分好みの排気音にできる」という事でしょう。
図太い音になれば、どんなバイクでもスポーティな感じがします。
音量はサイレンサーの太さや構造によっても違いが出るのですが、マフラーのブランドによってもある程度音の傾向が決まることが多いようです。
自分好みの排気音を楽しみたいという場合は、ユーチューブなどで目的のマフラーの音を聞いたほうが良いでしょう。
マフラー交換をする理由の一つとして、見た目の印象が変わるというものもあります。
自動車の場合は、マフラーカッターを取り付けることで、見た目の印象は若干の変化を与えることができるでしょう。
しかし、社外品マフラーに交換することで、バイクのイメージは大きく変わります。
チタンやカーボンなどの純正とは全く違う見た目になるので、印象を変えるためのカスタムとして一番に交換される部分だと思われます。
マフラー交換をするデメリット
・低回転域のパワーが無くなる
・振動が増える
・音量によっては車検に通らなくなる
まず、興味がない人からすれば、「うるさい」の何物でもありません。
人が「うるさい」という音をすべて消し去ったのが、車の電気自動車です。
しかし、車が近づいているかどうかが分からないという理由で、不自然な音を低速走行時に発するようになりました。
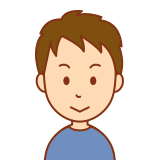
人間とは勝手なものですね(笑)
筆者は、暴走族が夜中に爆音を立てても、熟睡できるタイプです。
むしろ、最近の暴走族の爆音とやらが、大人しくなったような気もしますがね。
筆者の経験では、バイク走行中に歩行者から、石を投げつけられました(苦笑)
バイクや筆者にこそ当たってはいませんが、そういう頭のおかしい人もいるので、マフラー交換をするにしても注意が必要です。
社外品マフラーに交換することで、交換テインでぶん回しながら加速しているときは、速くなった気になるかもしれません。
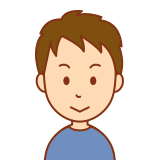
しかし、低回転トルクは薄くなっている感じがするので、メリットがあるのは高回転域のみでしょう。
もちろん、低回転域を犠牲にしないで、高回転の抜けが良くなるというマフラーも存在しします。
まとめ
中古バイクを買って新規で車検を受けるという場合も、新しい保安基準の対象となります。
カスタムのためにマフラー交換をするという人もいるかもしれませんが、見た目や音質にこだわるだけではなく、車検に通るかどうかについても確認したほうが良いでしょう。
車検の時にいちいち、マフラーを純正に交換するという手間が無くなれば、カスタムもさらに楽しいものとなるはずです。
疚しい気持ちでカスタムをするのではなく、誰にも文句を言われず堂々とカスタムすることに意味があると筆者は思っています。